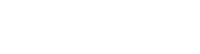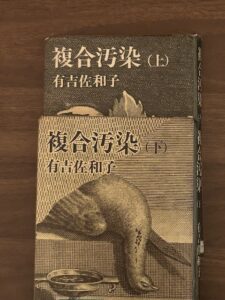こんにちは、東大和市ボディ&ソウルケア整骨院シエスタです
今日はミミズの話から
火薬と化学肥料の話
「ミミズの体内を通った土は普通の表土より
窒素が約5倍、リンは7倍、カリは11倍
そしてマグネシウムは3倍多い。
窒素もリンもカリウムも肥料と呼ばれる
元素であるのに、これが硫酸アンモニウム
過リン酸石灰、硝酸カリウムなどの
化学肥料となって
土に投げ込まれると
ミミズはたちまち死んでしまう」
ミミズがいる畑はいい畑っていうよね。
化学肥料を入れると
なんでミミズがいなくなるのか(?_?)
「化学肥料を使うとどうしてミミズは死ぬのか
硫安(硫酸アンモニウム)が農土に入って
作物に必要なアンモニアが吸収されると
土に硫酸が残る
過リン酸石灰を使うと作物がリン吸収した後
硫酸が残る。
塩化カリウムを使えば作物が
カリウムを吸い取った後に塩酸が残る
硝酸カリウムなら硝酸が残る
どの化学肥料を使っても土が酸性になってしまう
ミミズは酸性の土を嫌う」
なるほどね~
酸性が嫌いなんだ
アタシが借りてる畑も
ミミズ見かけないんだよね(;^ω^)
一部端っこにスギナが生えるから
そこは酸性土壌だとは思うんだけど。
でも石灰とかは入れない
土が固くなるし
なるべく自然循環で何とかしたい
と思っている(*’ω’*)
農業の近代化は
殺虫剤、除草剤、各種農薬がセットになっていて
化学肥料の驚異的な発達も
農薬の飛躍的な進歩も普及も
どちらも戦争と密接な関係があるそうで。
窒素肥料もカリ肥料も火薬の材料なんだって。
「1910年ドイツで水素と窒素から
アンモニウムを合成することに成功。
1914年アンモニアを硝酸に変えることに成功
1914年第一次世界大戦勃発
ドイツはアンモニアと硝酸の工業化、実用化に移る。
ドイツが開発した火薬を作る技術は
ドイツが戦争に負けてからは
化学肥料を作る技術として
「平和利用」されることになる。」
出たぞ~「平和利用」(-_-;)
世界中がドイツの開発した技術を受け継いで
肥料を作り始め
日本では1923年(大正12年)に
日本窒素がアンモニア合成を始めた。
日本窒素は明治41年創立
今も続いている会社です。
日本窒素と水俣病に興味のある方は
ググってみてください。
ここでは割愛しますね(;^ω^)
もっと時代を遡ると
日本でも火薬は作られていて
鉄砲を実戦に使い始めたのは
織田信長以来
関が原に近い滋賀県長浜にある
国友村が江戸時代を通して幕府直轄の
鉄砲製造を専業としたそうです。
国友鉄砲ミュージアムに行けば
火縄銃体感コーナーってのがあって
今も火縄銃に触れるらしいぞ(/・ω・)/
火薬はといえば
加賀藩が開発して幕府に納めていて
その作り方が途中まで堆肥の作り方と一緒。
「雑草を天日で乾燥し、人尿で湿らせ
蚕の糞をまぶし、家の床下を掘って
前記のものと土を交互に積み重ね
床板で押さえて一年おく」
ここまでが堆肥の作り方
ミミズを入れた土と入れない土だと
ミミズを入れたほうが硝酸が多かったそうで
硝酸・・・火薬の材料
ミミズさん、いい仕事してたんだね~
しかし、この後
「これを唐銅の釜に入れて、水で溶いて
かき混ぜながら煮詰める
そこに木炭粉と硫黄をつきまぜて固め
細かく刻み直して乾燥させる」
これで黒色火薬のできあがり。
堆肥は煮ないし乾燥させない。
火にかけたり、天日に干すと
ミミズ、バクテリア、カビが死ぬ。
それに木炭粉と硫黄。
これが堆肥と火薬の差。
似てるけど、途中まで一緒だけど違うもの。
私が通ってる有機野菜塾でも
堆肥つくりの授業やると思うんだよね(*’ω’*)
山の落ち葉と牛糞と土を交互に重ねて
足で踏み踏みしてから寝かせる。
そんな感じだと思うんだけど
どうだろなぁ~(*’▽’)
「第一次世界大戦の間に約40種類の
毒ガスが開発され、その多くが塩素系で
この時開発された毒ガスがのちの時代の
農薬となって田畑ばかりでなく
台所までしのびこみ人間の安全を脅かすようになる」
戦争のために開発された化学物質
戦争が終わったから不要になって
「平和利用」
平和って言葉はいいけど
ちょっと違う
やっぱり違うと思うのよねぇ~
んで、それって昔の話でしょ~と思いきや
しっかり今につながってる感じがするんだよね(-_-;)
・・・もうちょい続く
東京都東大和市の整骨・整体 シエスタ 院長 宇山由紀恵